「どうせ学歴」と諦めないでほしい
大学3年の夏、私はとにかく不安でした。
- 「高学歴じゃないと、大手企業なんて無理な」
- 「結局、学歴フィルターで落ちる」
- 「周りは有名大学の学生ばかり…私なんか勝ち目あるの」
でもそんな私でも外資系企業に内定し、複数業界の大手企業の最終面接まで進むことができました。
しかも、私の大学からほとんど採用実績がなかった企業に自力で内定を勝ち取りました。
- 大学にOBOGがいなくても、コネがなくても大丈夫。
- 就活は「学歴」で決まるわけじゃない。
- 「やるべきこと」をやれば、普通の大学生でも勝てる。
「今の自分には無理かも」と思っている人にこそ、この経験を知ってほしいです。
今日は、私が本気でやってよかった「逆転就活の戦略」をすべて公開します。
広告は一切なし。
私が実際に就活生のときに活用していた、お金を最小限に抑えながら就活を成功させるためのツールやセミナー、サイトなどの有益な情報を、余すことなくお届けします。
この記事の内容をすべて実行すれば、今までとは違った景色が見えるはずです!
就活の全体像を知る【就活本や無料のセミナーを駆使】

まずは、「自分は現在どの段階にいるのか」「今後どのように自分と周囲が動いていくのか」といった全体的なスケジュールを理解しておくことが大切です。
また、就活というものが一体何なのか、基礎知識や持っておくべき重要な考え方についても学んでおくとその後も生かすことができます。
ここでは、筆者が実際に使っていた講座と参考書をご紹介します。
Outstanding(アウトスタンディング)

アウトスタンディングとは、社会人のプロ講師による就活対策講座です。
全17講あり、いつからでも参加可能の無料講座になっています。
メリット
- 「一流企業内定水準の就活力」を身につけることができた
- 就活の全体像や知っておくべき知識を一通り学ぶことができた
- 早期から就活準備をしている優秀な仲間と出会え、モチベーションになった

Xで#アウトスタンディングとつぶやくと、受講仲間と繋がることができます。私はここで出会った仲間と自己分析の壁打ちなどをしていました。
デメリット
- リアルタイム配信のため予定が合わないことがある(アーカイブ配信はなし)
- ベンチャー企業などのあっせんがある
筆者は就活初期にこのセミナーを受講し、就活に対してより深く考えるきっかけになったとともに、就活の全体像を明確につかむことができました。
企業のあっせんなどは入ってしまうのですが、無料でここまで密度の濃い授業を受けられる機会はなかなかありません。
気になる講義だけでも聞いてみることをおすすめします!
おすすめの就活本
戦略就活メソッド
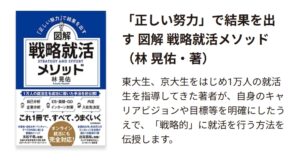
アウトスタンディングの講師の一人である林先生が書かれた本。
自己分析・企業分析~内定後の入社先企業選定まで、就活における全てのフェーズをカバーした内容となっています。
アウトスタンディングの講座内容の復習として読むのもおすすめです。
徹底的な自己分析【自分史とモチベーショングラフをひたすら書く】

「自己分析」は就活において最重要です。
自分のことを知らないままでは、企業選定も面接官へのアピールもうまくできないからです。
自己分析はたくさん手法があり、全てやろうとすると膨大な時間がかかってしまいます。その時間をSPI対策や面接練習に充てるためにも、時間をかけすぎないことが大事。
そこで、私が実際に行っていた自己分析の順序を具体例付きで解説します。
①自分史を書く
自分史とは、物心ついてから現在に至るまで、自分がどんな経験をしてきたのか、その経験が自分にどう影響を与えてきたのかを網羅的に振り返る方法です。
過去の出来事
→客観的分析(なぜそのように感じたのか)
→価値観の発見(今の自分にどう繋がっているのか)
の順に考えていくと分かりやすいです。
大きな白紙を用意して年表のように線を引き、出来るだけ具体的にたくさん書きなぐっていく方法がおすすめです。
自分史を書くメリット
- 自分の人生について深く理解し言語化できる
- 自分の価値観、考え方が変わったターニングポイントが理解できる
- 自分の根本となる価値観はどんなものか・それはいつ醸成されたのか知ることができる
自分史を書くうえでの注意点
- 作ることが目的にならないようにする
- 自分史を作る目的は自分を深く理解するためです。自分史を完成させること自体が目的になってしまわないように注意しましょう。
- ありのままを書く
- よく見せようとして嘘を書くのは本末転倒です!
- エピソードの大小は気にしない
- 些細な行動や小さなエピソードでも、それが価値観を表していたり、自分の価値観を変える出来事である可能性があります。エピソードの大小は気にせずにたくさん書きだしちゃいましょう。
②モチベーショングラフを作る
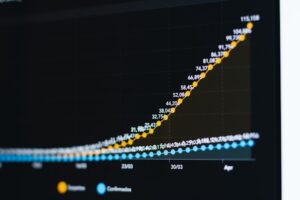
横軸に年代と年齢を設定し、縦軸にモチベーションの割合を0~100%で記入します。
「変化のポイントとなっている部分にどんな出来事があったのか」
「どんな感情になったのか」
「どう乗り越えたのか(乗り越えられなかったのか)」
といった観点から変化のポイントの共通点を探り、抽象化していくと、自分がどんな価値観に影響をされてきたのかが分かってきます。
また、自分がモチベーション高く物事に取り組める条件や、逆にうまくいかないときの条件なども見えてきます。
このような「モチベーションの源泉」は、ESや面接にそのまま使える材料となります。
③「Why」で掘り下げる
日ごろから感じた事や思ったことを「なぜ?」「なぜ?」と掘り下げていくと、自分ならではの価値観が見えてきます。
例えば、私は小学生の運動会の練習で2つ上の先輩にいじめられたことが悔しく、
得意な友達に協力してもらい放課後にその競技を猛練習した思い出があります。
この経験を「なぜ」で深掘りしていくと、私は
・『逆境や困難に直面すると逆にやる気が燃え上がる』人であること
・『仲間の力を借りながらさらなる高みを目指すことが好き』な人であること
と気がつくことができました。
このように、自分の行動や思考の抽象レベルを上げていくことで、共通する価値観が浮き上がってきます。
面接官に聞かれたときに、こういった価値観の部分まできちんと話す事が出来ると、面接官に良い印象を与えることができます。
④家族や友人にも聞いてみる(他己分析)
両親や兄弟、幼いころからの友人などに「私とはどんな人か」を聞いてみましょう。
自分が覚えていなかった幼いころのことを思い出せたり、他人から見て自分がどんな人として映っているのかを知り、自分を客観視できます。
初めは聞くのが恥ずかしいかもしれませんが、ぜひ勇気を出して聞いてみましょう!
【番外編】将来について考え始めた全学生に読んでほしい本
苦しかったときの話をしようか(森岡毅著)
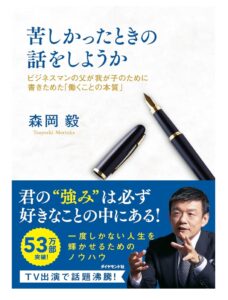
USJのV字回復をはじめ数々の企業のマーケティングに携わってこられた戦略家・マーケターの森岡毅さんが書かれた本。
実の娘さんにあてて綴った手紙の形式になっていて、情熱のこもったメッセージが詰まっています。就活・キャリア戦略を考えたり、人生の目的や自分の強みを見つけるうえでの指針となってくれた、私の人生にとって欠かせない大切な本です。
就活や将来について考え始めたみなさんにこそ、是非読んでいただきたいです。
エントリーシートに悩む時間をへらす【設問の型を知る・先輩をまねる】

就活のエントリーシート(以下ES)は、毎回ゼロから考えると膨大な時間がかかります。
でも実は、ほとんどの設問には「定番の型」があり、それを知るだけで大幅に効率化できるんです。
設問の型を知る
ESの設問は主に以下の3種類を聞いていることがほとんどです。
- ガクチカ
- 自己PR・強み
- 志望動機
それぞれについて、「この流れで書けばOK」という定番の型を解説します。

筆者はインターンから本選考に至るまで50社以上ESを出しました。その中で通過率がよかったESの構成と具体例をご紹介します。
ガクチカ
〈設問の例〉
- あなたが学生時代に力を入れた経験を教えてください。
- 今までの人生で力を入れて取り組んだことを教えてください。
〈ガクチカの型〉
- ガクチカの概要
- 生じた課題
- その原因と行った施策
- 結果
- 学び(字数に余裕がある場合)
〈ガクチカの具体例〉
〇〇事業を行う企業でのインターンで、大学生向けイベントの企画を成功させた経験だ。
私は□□の立場としてイベント企画を行ったが、集客に苦戦し売上が伸び悩んだ。
私はその原因を、一方的な企画と人手不足だと考え、施策として以下の二点を行った。一点目は、ペルソナの解像度を高める事だ。ペルソナに近い人物にヒアリングしニーズや思考プロセスを探った。二点目は、参加者からのFBを施策に取り入れることだ。参加者だけでなく、参加を断念した人にも話を聞くことで、自分たち目線ではなく相手目線でイベント企画を行うことを意識し続けた。
その結果、三回目のイベントでは集客を2倍にすることができた。
この経験から、仲間と協働し強みを生かしながら粘り強く行動を続ける力が得られた。
自己PR
〈設問の例〉
- あなたの自己PRを教えてください
- あなたの長所や強みを教えてください
〈自己PRの型〉
- 強みを一言で
- 強みを発揮した経験
- 挫折を経験したエピソード
- 上記の挫折に対し、強みを発揮して乗り越えたエピソード
- 結果
- まとめ
〈自己PRの具体例〉
- 現状維持で満足せず、上を目指し続ける「探究心」が強みだ。
- この強みを発揮した経験として、部活で数年ぶりの大会出場を果たした経験がある。
- 「~~」という目標を達成するため△△の練習を始めたものの、学年を超えたコミュニケーションが活発でない事で練習の質が下がっていた。
- その悔しさが自分に火をつけ、喫緊の課題である学年ごとのモチベーション格差是正のため、□□の施策を行った。
- 結果、部内のコミュニケーションや練習が活発になり、練習の質が上がったことで、1年後には数年ぶりの大会出場まで果たした。
- これは、さらなる高みを目指す探究心があったからこそ達成できたと考える。
志望動機
〈設問の例〉
- あなたが〇〇(企業名)を志望する理由を教えてください
〈志望動機の型〉
- なぜその業界なのか
- 自分が活躍できる理由
- なぜ数ある企業の中で御社がいいのか(ESの文字数が足りない場合はこの部分を削り、面接で聞かれたときに答えるのがベスト!
〈志望動機の具体例〉
- 志望理由は大きく三点ある。第一に、自身のビジョンとの親和性だ。私は塾講師バイトの経験から、誰かのできないをできるに変え、新しい挑戦をサポートできた時にやりがいを感じた。そのため、ITを用いた企業の課題解決を担うこの業界に魅力を感じた。
- 第二に、自身の強みを最大限生かせると考えるからだ。OB訪問を通じて、入社後は~~の仕事を行う上で、○○な力が必要だと考えている。そして、それには自分の△△の強みが活きると考えている。
- 第三に、貴社ならではの価値観に強く共感しているからだ。インターンで、貴社には△△の風土があると強く実感した。それまでのOB訪問や説明会においてもそういった価値観を持つ方が多いと感じており、そんな貴社であれば、自分の強みをより発揮してモチベーション高く働くことができると強く思った。

より簡単にすると、志望動機は「事業めっちゃ面白そう」「自分も活躍できそう」「社風や価値観もマッチしてるよ」ということを伝える!と覚えておきましょう。
先輩をまねる
ESの設問は基本的には似たものが多いですが、一部企業によっては少し特殊な設問があったりします。
そんなときは、ES通過した先輩のESをお手本にさせてもらいましょう。
ONE CAREER
先輩のESを調べる時は、ONE CAREERというサイトがおすすめ。
「ES・体験談」→「企業名を入れて検索」してみましょう。
内定者のみのESに絞って検索もできるので、通過率が良いESの構成を使ってESを書いていきましょう。
番外編:ESの管理方法
ESの締め切り日を個別に管理するのは大変ですよね。
私の場合は、Googleスプレッドシートを活用して一覧表を作成しまとめていました。

締切日を昇順で並び替えると、先に手を付けるべきESが一目瞭然。
また、テストやES提出が完了したものは「未」から「済」にするプルダウンを設定することで、視覚的に分かりやすくなります。
もしこちらのスプレッドシートのテンプレが必要な方がいたら、お問い合わせフォームから連絡してください。必ずお送りします。
とにかく人に会って話を聞く【OB訪問は百利あって一害なし】

就活は情報戦です。
特に、一次情報(直接得た情報)の方が信頼性が高いため、積極的に集めましょう。
OB訪問や社員と直接話せる説明会に参加すれば、企業選び・面接対策・入社判断まで役立つ貴重な情報が得られます。ぜひ活用してください!
OB訪問のやり方
OB訪問として一番身近なのは、大学のキャリアセンター経由で連絡を取ることが挙げられます。
それ以外にも、以下のサイトを使うことで他大学の現役OBOGとも話ができます。
就活に向けてダウンロード必須です。
ソクミーの勉強会に参加する
私が就活で行きたい企業から内定をもらえたのは、70%くらいSokumee(ソクミー)のおかげだと思っています。そのくらい全就活生におすすめしたい神サイトです。
完全無料で、これ一つ登録しておけばいつでも気軽に面接練習ができます。
またソクミーでは、難関企業に内定した現役の大学生やOBが開催する「勉強会」があり、これに参加することで業界や企業に特化した対策ができます。
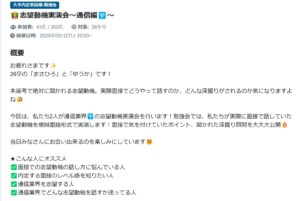
「ただの元人事」さんの公式LINEを追加するとソクミー登録用のリンクが出てくるので、そこから登録できます。
OB訪問で聞いておくべきおすすめ質問
続いて、OBOG訪問で聞いた内容を、どう面接で活かすのかについてお話をします。
面接って、答えるのが難しい質問が突然おそいかかってきたりしますよね…
臨機応変に対応をする力ももちろん大切ですが、面接の前にできる最大限の事前準備をしておくと気持ちが楽になります。
ここでは、『面接で100点の回答をするためにOB訪問で何を聞くべきか』について、私が実際に聞かれて困った面接の質問と回答例を用いて2つご説明していきます。
OB訪問で聞くべきこと①:企業の「弱み」
面接では、企業の弱みやもっとこうあるべきだといった意見が求められることがあります。
そのため、「○○さん(OBOGの名前)は御社で働く中で「もっとこうしたらいいのに」と思う部分とかは合ったりしますか?」といった形でやんわりと聞いておくと役に立ちます。
〈とあるIT企業最終面接にて〉
面接官:『〇〇さんが弊社に対して「もっとこうなってほしい」といった希望や求めることはどんなことがありますか』
学生:『年次問わず意見交換できる機会がさらに増えたらいいなと考えます。何名かの社員さんにお話を伺う中で、「〇〇」のお話を伺いました。そのため、~~といった機会がありましたら、御社においてより自分の強みを発揮できると考えます。』
OB訪問で聞くべきこと②:キャリアパス
面接官は「長く働いてくれる人材かどうか」を注視して学生を見ています。
そのため、どれだけ具体的に入社後のキャリアパスを描けているかといったポイントが見られるのです。
OB訪問では、OBOGのこれまでのキャリアの変遷や今後の希望を聞くとともに、可能であればその先輩たちが就活の際に面接官に伝えていたキャリアパスがあれば教えてもらいましょう。
〈とあるメーカーの二次面接にて〉
面接官:『〇〇さんが弊社に入社したらどんなキャリアを歩みたいですか』
学生:『◇◇を目指し、□□にまずは力を入れていきたいです。中でも、以前お話を伺った○○さん(OBOGの名前)は、「~~」とおっしゃっており、そのようなキャリアの築き方にこれまでの自分の経験や強みとの親和性を感じ魅力を感じました。そのため、私は△△といった強みを最大限発揮し、この分野の事業拡大に貢献していきたいです。』
スキマ時間に面接練習とGD練習【ソクミーをフル活用】

面接・GD練習は「場数」と「事前準備」が大切です。
特に場数を増やすためには、前章で紹介したソクミーを使っていました。
ソクミーを使った面接・GD練習のやり方
「練習相手を募集している就活生の部屋に参加する」もしくは「希望する時間に部屋を作成する」ことでマッチングが成立。zoom上で面接やGDの練習を行うことができます。
それぞれの手順を解説していきます。
①練習相手を募集している就活生の部屋に参加

- ソクミーにログイン
- 「予約検索」をクリックし、希望する時間帯やカテゴリを入力
- 気になる部屋を見つけたら、「詳細」をクリック
- 「部屋に参加する」をクリック
- その後、メッセージでZoomリンク送付などのやり取りを個別で行う
②希望する時間に部屋を作成

- ソクミーにログイン
- 「新規部屋作成」をクリックし、タイトルや参加上限人数、日時や概要(面接で見てほしいポイント、志望業界など)を入力
- 「プレビュー」をクリックし、確認後に公開する

面接では、一貫した強みと個性を伝えることが大切です。私の場合は、面接官に「真面目だけど実は誰よりも熱量と行動量が大きい子」というイメージを持ってもらおうと意識して面接に挑んでいました。
PDCAを回し、面接の勝ち筋を見つける【Googleドキュメントを使って復習】
面接はやって終わりではなく、必ず復習をしておきましょう。
実際、面接で上手く答えられなかった質問の回答例を作っておいたおかげで、別の企業の面接ですぐに納得のいく回答ができた経験があります。
Googleドキュメントを使った復習のやり方
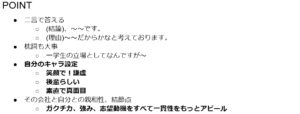
私はこの画像のような形でGoogleドキュメントを活用し、面接で聞かれた質問や反省点をまとめていました。(気づいたら合計124ページになっていました笑)
紙に書くのも良いですが、デジタルツールを使うと以下の点で便利です。
- 検索機能で過去の記録をすぐに見つけられる
- ディクテーション機能で音声入力ができる
- タブを設定すれば、必要な情報に素早くアクセスできる
特にオンライン面接では、カンペとして活用するのもアリです。タブを設定しておけば、深い回答をスムーズに伝えられます。
ただし、その際は画面の分割機能を使い、ドキュメントをカメラの近くに配置することで、自然な目線を維持しましょう。
そして面接練習やオンライン面接で何度も話しているうちに、対面の面接においても言葉がスラスラ出てくるようになります。
上手くいかなかった場合でもその失敗を次に生かす心持ちで、どんどんPDCAを回していきましょう。一度でもその「流れ」をつかめるようになると、面接が本当に楽しくなります!
まとめ
ここまで読んでくれたあなたなら、普通の大学生でも就活で逆転できる方法がしっかりと理解できたはずです。
ですが、知識を得るだけでは何も変わりません。
大切なのは、今すぐ行動に移すことです。
- まずは、エントリーシートの「型」を意識して1社分書いてみる
- 先輩のESをチェックして、自分の表現をブラッシュアップする
- 面接対策として、Googleドキュメントで質問と回答を整理する
どんなに小さな一歩でも、積み重ねれば必ず結果は変わります。
皆さんの就活を心から応援しています!
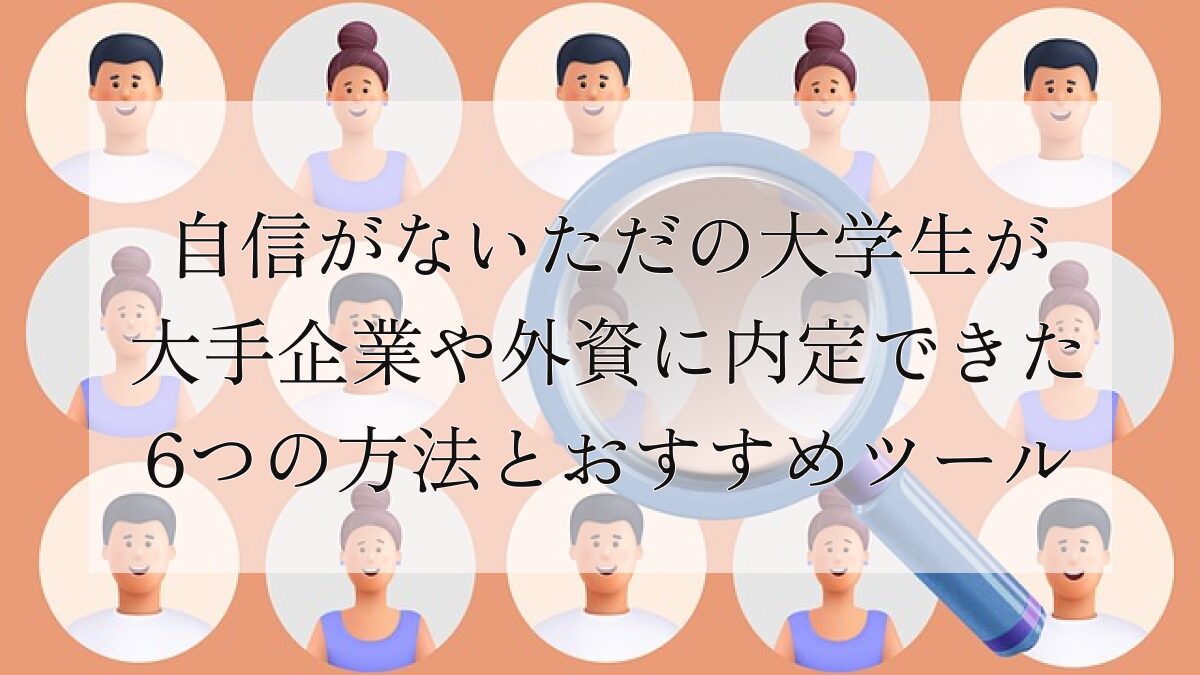

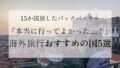
コメント